スタッフブログ一覧
食い止める!
2024年07月17日
食い止める。
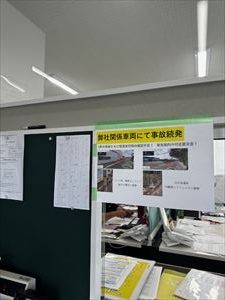
7月に入り立て続けに物損事故を発生させてしまった。
一件は、お客様付近の電柱にバック時に接触。
もう一件はお客様構内の出入り口をトレーラーの内輪差で接触。
両方とももう少し注意深く運転をしていればと感じる事故である。
バックモニターなど様々な安全器具は付けるようにしている。
ハード面をいくら取り揃えても社員教育、安全教育などしっかりしていかなければ意味がないことを再認識させられた(-_-;)。
毎月、安全会議を行って様々な事例の水平展開、ディスカッションとやれることはやっているつもり。
だが毎回事故が起きるたびに足りなさを感じる。
永遠のテーマ・課題であり、無事故は常に追い求めるものであることは認識しているものの難しさを感じる。また初心に還って教育していこう!
1300円で夫婦でウナギを喰らう
2024年07月01日
最近というか昔からだけど「うなぎ」は高い。
 先日、一色のさかな広場に朝食を食べに行った際、横のお店で生のウナギが売られていた。
先日、一色のさかな広場に朝食を食べに行った際、横のお店で生のウナギが売られていた。
一尾【1800円】・・・・・う~ん、・・・値切ってみた。
1300円にしてくれるといったこともあり一尾購入。
ウナギを焼くのは初。YouTubeなどを見てみると職人さんが鉄の串を刺して炭火での焼き方が学ぶことができる。
しかし、我が家は一般家庭なのでもちろん串はない。じっくりと網焼きしか手がないので早速準備。
今年の年始に震災に見舞われた『珠洲市』で以前購入した“長七輪”が本来のポテンシャルを発揮するときが来たのだ。
焼く前の頭付きのウナギはその長七輪からもはみ出るほどの大きさ。
肉厚も記憶にかすかに残るお店屋さんで食べた鰻と同じくらいのすばらしさ。
焼きあがった鰻は写真のとおり完璧。味も言うまでもなく完璧。
こりゃ~ウナギ屋さんはしばらく行かなくなるだろうな。
マジでうまかった。
イキイキとした女性
2024年06月25日
奥様も京都に住む息子のところへお出かけになったこともあり、豊橋へ。



学生時代の同級生が少し前にマフィン屋を開業した。
「BAKE ME UP」英語が得意な彼女が考えた非常に耳触りの良い店名だ。
10数種類のマフィンが並んでいて、中には米粉で作った僕には全く無縁のヘルシーなものもあったが・・・
最終的には4つも食べてしまい、ヘルシーもへったくれもない。
数年ぶりにあった彼女は生き生きしていて楽しそうだった。
やりたいことをしている人はやっぱ最高だ!
バイクでの道のりは約3時間。「ちょこちょこ来るね」といった社交辞令はなしにして「また来るわ」と言っておいた。今の時期、またバイクで行くようなことをすれば僕自身もヤバいし、70歳オーバーのバイクは即死するだろう。
また涼しくなったらおっさんたちを連れて行こう。
第6回安全会議
2024年06月15日
6月8日、定例の安全会議を開会しました。

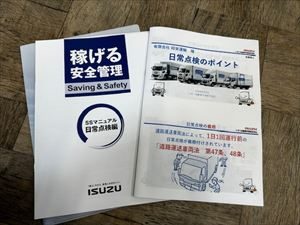
そう、今回はいすゞ自動車さんをお呼びしての【整備講習】をメインに行いました。
冒頭に「よろしくお願いします!!」と全員で挨拶をしたところから終始真剣に学ぶことができたように感じました。
特に乗務前点検では社歴の長い方もしっかり聞いていてくれたのは良かったと思います。
「分かっとるでいいわ」これが成長を阻害するNGワード。
分かっているなら後輩にしっかり教えてあげる。そうすることでさらにその知識は深まる。
自社の構築していきたい企業文化は「相互成長」。それに近づけられるいい活動でした。
常滑運輸、やるなぁ~(@_@)
2024年06月10日
同市内のライバル 兼 お客様 兼 仲間の企業、【株式会社 常滑運輸】
やりやがった~( ゚Д゚)
ドリームプロジェクトという企画に賛同して新車大型トラックに全面プリントを施した車両を導入された。絵柄はというと



まず後ろには「登り窯の煙突」右サイドには「りんくうビーチ」左側には「土管坂」と古き良き常滑と常滑の新しさを感じられるデザインになっていて、めっちゃかっこいい。 先日も街中を走っているのを見かけたが、かなり目立つ( ゚Д゚)
細かくて見えないと思うが、車両後方部分に描かれているのは「子供たちに夢」である。
きっとこの「子供たちの夢を背負って走る」がドリームプロジェクトの主旨なのだろう。
我々が子供の時に描いていた夢と同じような年代を感じさせないものや「ユーチューバーになる」など新しく子供たちの夢にランクインした業種や生き方もあり面白いものだった。
披露会には関係者や社員、多くの子供たちも来ていて賑やかな感じでそれもまた良かった。
新社長に変わり、若い経営幹部がけん引する常滑運輸、負けないように頑張らねばと感じる活動でした。
まぁ~うちは平ばかりで描くところないんですけどね(-_-;)
P.S.
あの車乗っているドライバーさん、気ぃ~使うだろうな~(@_@)
正しく積んでいい仕事しよう。
2024年06月08日
6月の安全会議にて「製品にあった荷積みと固縛」というタイトルでの講習の一コマ。

 「まぁ~普通じゃん」と思うだろう。
「まぁ~普通じゃん」と思うだろう。
確かに普通である。
荷縛りにおいては最短距離で締め上げることで緩みもなくしっかりと力を伝達させ荷物を固定することができる。写真の角度がいまいちなので分かりにくいと思うが、最初から「荷縛り位置」を意識した場所に積み込まれており、数ある製品の中から出来る限り高さの合うものを組み合わせてある。
終わったこの荷姿を見れば誰でも普通に積んでいるように思う。しかし、意識をもって積み込まなければこうはならない。
そういった細かい話をしても「当たり前」と思えるような教育をしていこうと思う。
こういった作業を当たり前にやってくる自社ドライバーの良さをこっそり楽しんでいます。
運送業はA地点からB地点へ物を移動させるという付加価値がつけにくい業務だと思う。運ぶクオリティーもこういった部分でしか感じることはできないし、社会や一般の方、お客様にはなかなか認知されない。
まさに縁の下の力持ち的な業務だ。ライフラインと言われる電気・ガス・水道の様に我々の業務は「社会的インフラ」であるので、「ありがとう」を言われない、あって当たり前、そんな存在を目指してこれからも頑張っていきます。
籾〇さん、いい仕事してるね!thanks!!
壁を作るということ
2024年05月13日
人と人との間にて壁が一度できてしまうと壊したり超えるのにも多くの時間や労力がかかる。
個人的には壁を作っているつもりはないのに相手からした場合、壁に感じてしまうこともあるのだと思う。
業務を速やかに遂行したり、全体感でモノを進めていくときには権限を集約し、誰かが決定権をもって進めていかなければならない。
そうするために役職などを持ったり与えたりして会社を組織化していく。そうする中で役職といった部分がイコール壁みたいになってしまいがちだ。
いざという時にコミュニケーションだけでなく、日々のコミュニケーションがその壁を少しでも緩和していくことができるのだと思う。そういった関係性づくりこそが重要となってくるとよく感じる。
人間同士の関係性における壁は油断しているとすぐにできてしまうものだが、建物の壁はそうやすやすとは出来ない。今回のGWを全部捧げたのが、ガレージの一部を壁にする大作戦だ。
友人の大工に頼んでウッドショック後の高騰しまくった木材を限りなく安く売ってもらい、梁を入れてOSB合板で仕上げていく。
この距離で見る壁は寸分狂わない採寸とプロ顔負けのカットしたように見えるが、向こうが見えない程度の隙間がちらほら・・・(-_-;) それが素人が作り出せる【味】なのだ。
壁を作るのは難しいのだ。

お気に入りの漫画の棚ができて、脚立の上で漫画を読む時間が増えそうだ。
キレました(# ゚Д゚)
2024年05月06日
キレた~!!!!
 フロントブレーキのブレーキワイヤーが(-_-;)(-_-;)(-_-;)
フロントブレーキのブレーキワイヤーが(-_-;)(-_-;)(-_-;)
僕のバイクは左足でクラッチ操作をするタイプの車両。チェンジは左手で行う。
ハーレー乗りにはおなじみの「ノンロッカークラッチ」です。
フロントブレーキレスになると【スーサイド】と呼ばれるものになる。suicide=自殺
1速に入れ、繋がった時にフラついてしまうとバイクだけで走っていってしまう。フロントブレーキをかけることができればエンストで止めることはできるが、そのフロントブレーキがないのはかなり怖い。
何はともあれ早く直さなくては・・・。
なかなかいい取り組み
2024年05月04日
ツーリングで吉良のワイキキビーチへ向かう途中、ファミリーマートに立ち寄りコーヒーブレイク。
【ファミリーフードドライブ】と書かれたボックスが設置してあった。
各家庭で不要になったり、賞味期限が近いものや食べきれないものを回収するボックスのようだった。
必要としている方々へ配るのだそうだ。
地域にもフードバンクなるものがあり、企業の売れ残りなどを寄付し、子ども食堂に提供したり配ったりする活動がある。
皆の利用するコンビニエンスストアで直接やり取りできれば効率は良さそう。
どの様に誰が誰に配るのかが疑問ではあるが、良い取り組みだと思う。
様々な事情により貧困は広がっていると話を聞いた。100人に一人の割合で家で食事がとれず、給食だけを楽しみにしている児童がいるそうで、自分の周りにはいないため衝撃的だった。
親の就労状態や家族構成が問題なのであろうか?これだけ人材不足と言われているわけだから仕事がないなんてことはないのに【非就労で貧困】がよくわからない。
大人が自らの選択で貧困を選択するのは別に気にしないが、それにつられて子供たちが苦しんでいるのはよくないと思う。それを助けようと生活保護を支給しようとするとそれを目当てに非就労が増える。その怠けた人たちの生活保護を行うために働いている人は税金を取られる。
相互扶助の精神で世の中が成り立っているので、わからないでもないが、みんなが頑張る中でこそ相互扶助の精神は活きてくるのではないだろうか?
いちいち考えさせられるな~(-_-;)
せんえつながら
2024年05月03日
せんえつながら・・・別に謙虚にしているわけではない。友人が始めたラーメン屋の名前だ。
焼肉屋さんを2店舗やっている高校時代からの友人が一宮駅のすぐ近くで始めた。
 写真を見ればかなりの老舗感を漂わせているが、オープンしてまだ一年ほど。(笑)
写真を見ればかなりの老舗感を漂わせているが、オープンしてまだ一年ほど。(笑)
ゴルフで会うたびにラーメンのスープに関するこだわりを聞かされていたが、生憎平日しかオープンしない為、全然食べることができなかった。
今回のGW2024.5.3初となる祝日オープンをするということで行ってきました~。
THE中華そばといった見た目で、味も濃い目で好きな味でした。めちゃめちゃおいしかった~
ラーメンの写真は撮り忘れ(-_-;)
同じレシピで作っていても冷まし方や何やらで微妙に味が変わってしまうといつも調整に苦労しているといっていた。その苦労の甲斐あってオープン前から並ぶ人も。
もうちょい近くにあればちょこちょこ行きたいところですが、一宮はちょっと((+_+))
ラーメン好き、一宮付近でお昼に暇がある人是非一度行ってみてください。
チャーシュー丼も美味かったですよ!